EXHIBITIONS | |||||
 | |||||||||||||||||||||||
~3月29日(火) | |||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||
PRISMは自然の光をスペクトルに分解し初めて人間に「七色の光」を認識させた。 「グループ展PRISM2011」の7名のアーティストは多種多様なバックグラウンドを持つ。 それぞれの作品の視点の豊かさは、観客を多様性の世界へと誘い、作家をかつて自らの作品の認識し得なかった世界へと導く。 本展は、観客にも作家にも、新しい世界を発見する機会になったのではないだろうか。 「新しい発見」は「新しい創造」の道標にもなる。19世紀後半、PRISMの発見で印象派の先駆者が不可視の世界に光を当て、新しい造形表現へと道を拓いていったように。
麻谷 宏 麻谷は本展ではドローイングを出品している。座標を思わせる縦軸を画面の中央に、それに対し直角に横軸が画面を分割する。まるで方向や位置を指し示す座標軸である。 背景には墨で、にじみやぼかしで偶然に生じる形態を配している。自然空間を表象しているのだろうか。下部には数本の数直線が並列に並べられ上部の有機形態と対照をなす。あたかも、自然と人間の関係を座標軸上に位置付けようとしているかのようだ。麻谷の言葉を借りれば、「人間も悠久の時間とエネルギーの中に存在していることを、五感すべてを研ぎ澄まして認識することから物事が始まるのではないだろうか。」この座標は時間とエネルギーと人間の関係を象徴しているかのように思える。 麻谷の作品には日本の美意識の匂いが漂う。日本文化に根ざした精神が垣間見える。それは、西洋思想に見るロゴスによって世界が捉えられるという人間の知性への確信の世界ではない。自然と対立せず自然との共存や調和を求めている。日本人の時間的な世界観に根ざした、移ろい行く世界に対する味わいだ。彼はその関係性のなかで生起してゆく自己の「意識」を捉え、外側の世界との経験を座標軸に刻む。論理を超越した座標軸に。
Lisa Gray グレイが描くすべての人物像は3等身ほどの体躯に矮小化された女性である。その小さな肢体には。巨大な頭部が載り、顔に比して異常に大きな眼が張り付いている。その目は大きく見開き前面を凝視する。人物はすべて正面を向き、その人物の生きざまを象徴する衣装を纏っている。 彼女は絶頂期に予期せぬ不運に見舞われ、人生を翻弄され、非情な最期を遂げた女性(マリリン・モンロー、アメリア・エアハート、フリーダ・カーロ等)を好んで題材にしている。グレイ自身、若くして癌に侵され闘病生活を余儀なくされた。美術館での個展、好意的なレビューなどを経て、美術家として認めらようとした矢先であった。自身の人生を彼女たちに重ねわせているのだろうか。グレイのカリカチュアされた肖像は、彼女自身の化身ででもあるかのようだ。 フォトショップで操作され、デフォルメされた肖像は、苦渋を内に秘め、歪んだ人生を表出した作品となっている。それは絵画と見紛うばかりの写真表現である。
しまだそう 作品「見てるだけ・7」には、記号や文字、旗、山、動物、人間のものと思しき内臓の一部、数十年もタイムスリップをしたようなイメージがところ狭しと画面に描き込まれている。 しまだは、異なった歴史的時間帯からのイメージを、同一空間上で遭遇させ、時間、空間を飛び越えてお互いのコミュニケーションを仕掛けている。西洋絵画のパースペクティブを無視したそれぞれのイメージは、複数の視点で、交錯し、絡まり、複雑な緊張感のある不思議な世界を構築している。 それはまさしく、しまだの社会との接触により獲得したレキシコンから任意に選ばれたビジュアル言語が、矩形の平面に「物語」を生成していると言えよう。確かなデッサン力と構成力に裏打ちされた表現は観客に有無を言わせず、しまだの世界へと導く。
杉本晋一 杉本の絵は一見すると抽象画に見える。地と図の区別がない。中心や焦点になるようなイメージがあいまいな点、ある意味「オールオーバーペインティング」と言ってもいい。しかし、カラーフィールド派や抽象表現主義のように抽象ではなく、具象である。具象である限り、純粋に絵画の中に一定の中心を持たせないことは不可能であろう。しかも、イルージョンは排除されていない。ここでは、グリーンバーグが唱えた絵画の平面性などとは無関係である。杉本が求めているのは、現代の社会における力関係が拡散し平均化するといかなる状態になるのかを視覚化することである。また、かつて排除されていた物語性をもその「オールオーバー」な画面に取り込んでいる。 杉本は相反するものを対置することによって画面に緊張感を生み出している。暖色と寒色。柔と硬。人間(自然)と機械(人工物)。そこでは、対極のものを対峙させ人間が機械に苛まされているシーンが繰り返し、描写されている。20世紀の文明が夢見た機械(科学)による明るい未来は無残にも人間を裏切った。21世紀に循環型社会へのパラダイムシフトの必要性が言われて久しい。杉本の作品には、大量生産、大量消費、大量廃棄物そしてそれらに伴う公害などを産み出した20世紀の反省と同時に21世紀への警告が読み取れる。
布原美帆 布原は本能に任せて描くアーティストである。「瞑想状態の時、形が降りてくる」という。形而上世界から「一条の美の光」が射しこんでくるのであろうか。ミューズの神が憑依し、お告げを受けそれを具現化する巫女のような役割が布原の肉体のようだ。研ぎ澄まされた感性で本能に従ってキャンバスに痕跡を残す。時に、自らが印した形態すらそれを認識出来ない場合もあると言う。 作品「わたしのなかのかみさま」は官能的で、無垢の少女がふしぎなエロチシズム放つ。布原は、本能的に自己の内面に問いかけ、無意識の世界を渉猟し、遭遇するイメージを「心の眼」でとらえ現前させている。不思議な能力を持つ希有なアーティストである。
林和音 ギャラリーの戸口に近い中央には、作品 「つながる穴」が天井から吊るされている。瓢箪型をした形態は、魚籠を思わせる。針金、枝などで骨格を造り上げ、それに棕櫚縄や羊毛などを絡ませたり巻きつけたりしてある。近代的な彫刻の概念である量塊、量感はない。「穴」と言っても負の空間を有しているわけでもない。というのも対比すべき量塊が喪失しているからだ。 ワイヤーによって切り取られた空間が、その空間を包摂し「穴」と呼ばれる空間を構築する。それは正でも負でもない空間だ。それは外の空間をも内に取り込む。また外の空間はうちの空間をも包摂する。林の言う「うちも外もつながるようなイメージ」である。さらに続けて、「人それぞれの価値観の違いによって存在する曖昧なものに魅力を感じる」と林は言う。まさしく穴が穴を形成し穴が穴を消滅させている。穴と呼ぶにはあまりにも曖昧な存在である。そこにこの作品の魅力がある。
MARUYA マルヤの作品に接した時、西村計雄の作品を想起した。上下に時には対角線上を素早く走るストロークが記憶を呼び起こしたのだろう。しかし西村のタッチは一陣の風を感じるが、マルヤの筆運びは、鋭く深く心の襞にまで入り込む。西村の春のような穏やかな色彩はなく、教会の暗闇の中で浮かび上がるステンドグラスの神々しさが、荘厳さが、その色彩にはある。 マルヤの花に視力を得た新生児の新鮮な驚きをみる。闇から引き出された新生児の目は色彩の洪水に見舞われる。無垢の記憶に刻み込まれた色彩をマルヤは丹念に掘り起こしているかのようだ。 マルヤは言う「私にとっての花は、音楽家にとっての音符であり、詩人にとっての文字のようなものだと思っています。旋律や言葉が生まれた瞬間に、ただの音符や文字はその姿ではなくなり、美しい調べとなって、音楽に、詩になるように、花も花でなくなる。そして、絵でさえなくなってもよいと思っています。」そこには形態を離れ新生児の感受した初々しい色彩が、ただ崇高な響きを放っている。
コンテンポラリーアートギャラリーZone 代表 中谷 徹 | |||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||
 | 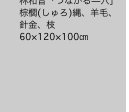 | ||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||